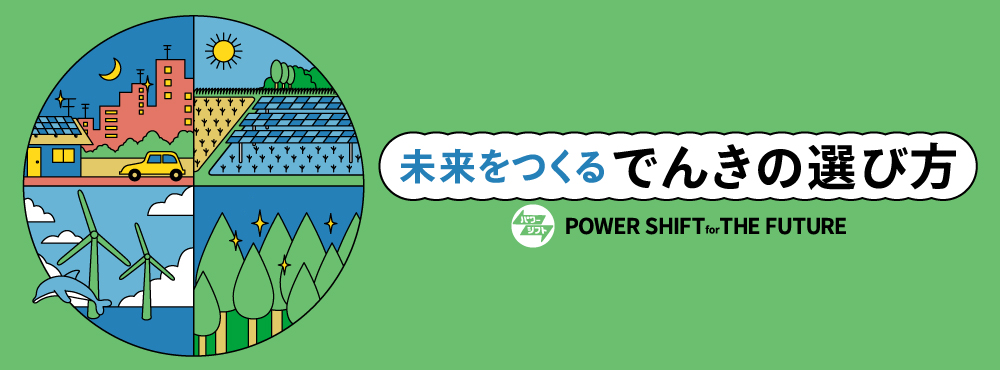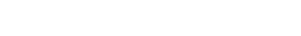株式会社トドック電力

コープさっぽろ
コープの電気は選べる二つの電気があります。
電気の未来を選ぶのはあなたです。
トドック電力サイト https://todock-ep.sapporo.coop/
| 供給エリア | 北海道(離島を除く) |
| 小売供給の開始時期 | 高圧:法人向け(供給中) 低圧:法人向け(供給中) 低圧:家庭用(供給中、コープさっぽろ組合員限定) |
| 事業対象(販売先) | 生活協同組合コープさっぽろ組合員 |
| 電源構成 | 再生可能エネルギー100%メニュー (FIT電気にFIT非化石証書(トラッキング付き)を付与) FIT(バイオマス)100% *その他メニューもあります <2022年度実績> 同上 <2023年度計画> |
| 電源の調達先(補足) | 市民電力からの調達:なし 高圧買取:不可 一般家庭の太陽光(余剰)買取:不可 卒FIT太陽光買取:可(組合員かつ電力供給の方対象) その他:既存の電力会社と常時バックアップ契約は行なわない |
| 再エネ供給能力の見込み | 2021年4月より再生可能エネルギー100%メニューにおいて、FIT電気(バイオマス)にFIT非化石証書を付与することで再生可能エネルギー100%の供給体制を実現 |
| 電源構成などの開示・表示方法 | ホームページにて公開 |
| 需給調整 | 委託先 |
| 会社情報 | 本社所在地:札幌市中央区北8条西18丁目35-100 エアリービル7階 設立年月日:2015年7月1日 代表者名:代表取締役 小松 均 資本金:2億円(資本準備金含む) 現在の事業内容:小売電力事業を目的として設立 小売電気事業者登録番号(登録日):A0191(2016年2月23日) 株主:コープトレーディング株式会社 89.59%、株式会社エネコープ 5.41%、 伊藤忠エネクス株式会社 5.00% |
| お問合せ | URL:https://todock-ep.sapporo.coop/ TEL:0120-012-877(月~土9:00~18:00/日曜・年末年始を除く) |
【公式】トドック電力 – 北海道の新しい電力会社 コープのでんき (sapporo.coop)
トドック電力は2016年6月、「グリーンエネルギーからの電力を家庭で使いたい」、「電力が自由に選べる社会を実現したい」という組合員さんの声から生まれました。2021年4月には再生可能エネルギー100%メニューにおいて、FIT電気(バイオマス)にFIT非化石証書を付与することで再生可能エネルギー100%の供給体制を実現しました。 再生可能エネルギー(FIT電気+FIT非化石証書)は、原発や化石燃料に替わって地熱・バイオマスなど自然の力を利用したエネルギーです。私たちは再生可能エネルギー(FIT電気+FIT非化石証書)の供給を通し、持続可能な社会を目指します。
これからも環境を重視する北海道のエネルギー企業として、組合員のみなさまのお役立てるように前進してまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
(2016年6月、2022年3月更新)